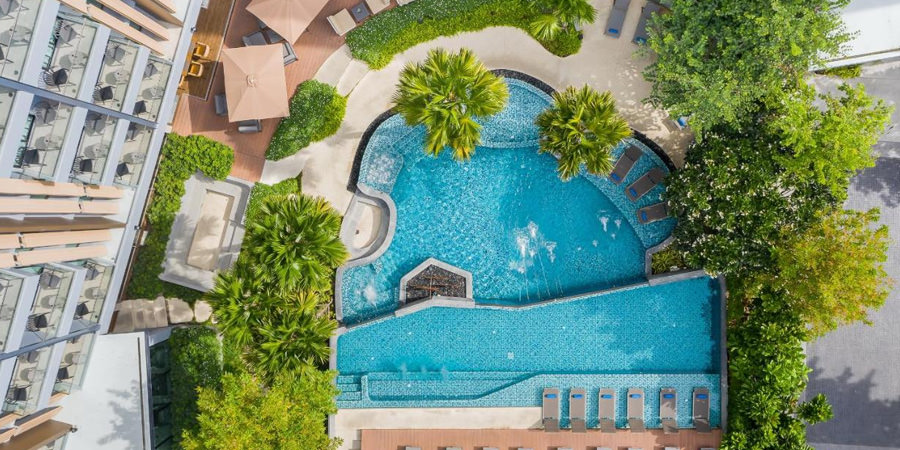インディカとサティバは存在しない?最新研究が示す“大麻の本当の分類”とは
大麻について語ると必ず出てくる言葉、「サティバはハイになる」「インディカは眠くなる」。多くの大麻薬局でもこの分類が説明に使われ、旅行者や初心者にとっては“品種を選ぶ目安”として語られています。しかし、自分が現地で多くの品種を比較してきた限りでは、この分類だけで効き方を判断するのは難しいと感じています。実際、近年の学術研究では「サティバ/インディカという分類は科学的根拠が乏しい」という報告が増えています。(引用:米国国立医学図書館)
そろそろサティバ=ハイ、インディカ=チルって都市伝説を信じてる大麻愛好家を減らさないといけない。今現在はその品種に含まれるTHC・CBD・テルペンの組み合わせとバランスによって効能が決まる。だから、インディカかサティバかではなく「自分がどんな気分を求めるか」で品種を選ぶのかが基本です
— Kei | タイに住む大麻盆栽家 (@smallnycer) November 10, 2025
自分がタイでさまざまな花を試してきた経験でも、「インディカだから眠い」「サティバだからハイになる」という感覚はほとんど当てはまりませんでした。実際には、THC・CBDの比率、そして品種ごとに異なるテルペン(香り成分)の組み合わせによって、体験が大きく変わっています。
最新の研究では、現代の市販大麻のほとんどが複数の系統が交配された“ハイブリッド”であり、純粋なインディカ/サティバはほぼ存在しないとされています。(引用:米国国立医学図書館)
ではなぜ、科学的に根拠が薄い分類がマーケティングとして残り続けているのか。その背景には、18世紀の“形の違いだけで分類された植物学の歴史”が関係しています。この記事では、最新の研究を踏まえて「サティバ/インディカ分類はなぜ崩壊したのか」を整理し、これからの大麻選びで本当に見るべき指標(THC比率・テルペン構成)について丁寧に解説します。
目次
1:「インディカ」「サティバ」の分類はどこから来た?」
自分が現地で多くの品種を見てきた限りでは、大麻薬局の説明で「インディカ=チル」「サティバ=ハイ」という案内が今も一般的に使われています。しかし、そのルーツをたどると18世紀の植物学に基づく“見た目の分類”であり、現在のような精神作用の違いを示す科学的根拠はありません。
当時、スウェーデンの植物学者カール・リンネが産業用ヘンプを「サティバ(Cannabis sativa)」と分類し、後にフランスの博物学者ジャン=バティスト・ラマルクが、インド原産で背丈が低い品種を「インディカ(Cannabis indica)」と呼びました。この分類はあくまで植物の外見的特徴に基づくものであり、現在一般的に語られる作用の違いとは無関係です。
その後、利用目的が嗜好・医療へと広がる中で、「姿が違えば効き方も違うはずだ」という解釈が文化的に広まり、現代のイメージにつながっています。自分が大麻薬局で購入者に説明される場面を見ても、この歴史的経緯が誤解のまま残っていることを感じます。
最新研究が示す「インディカとサティバにDNA上の差はない」
近年の遺伝子研究では、従来の分類に科学的根拠が乏しいという指摘が続いています。自分自身も現地で多くの品種を比較してきましたが、外見やラベルと実際の体感が一致しないケースは非常に多いです。
カナダやアメリカの研究チームは、数百種類の大麻を遺伝子解析した結果、インディカとサティバに明確な遺伝的な境界は存在しないと報告しています。実際に、市販されている「サティバ」とラベルのある品種でも、遺伝子的にはインディカ由来の要素を多く持つケースが確認されています。(引用:米国国立医学図書館)
つまり現代に流通する大麻は、ほぼすべてが複数種が交雑したハイブリッドであり、「サティバだからハイ」「インディカだから眠くなる」という判断基準は科学的には成り立ちません。
交配が進み、分類は“名前と見た目”だけが残った
自分が大麻薬局で栽培者の話を聞く限りでも、1970年代以降は多くの育種家が意図的に交配を重ね、香り・THC濃度・収量などを調整してきた流れがあります。その結果、現代の品種はほぼすべてが複数系統が混ざり合った交雑種です。
現在使われる「インディカ優勢」「サティバ優勢」という表現も、体感の傾向を簡易的に示すためのラベルに近く、遺伝的な分類としては正確ではありません。実際の体験を左右するのは、以下のような要素だと感じています。
栽培環境/カンナビノイド(THC・CBD)構成/テルペン比率/個人の体質
これらの要素によって同じラベルでも体感が大きく変わるため、従来の分類だけでは不十分です。これから大麻を選ぶうえで重要なのは、「どんな成分が、どんな気分を生むのか」を理解する視点です。これは現地での体験を重ねる中で、自分自身が最も強く感じているポイントでもあります。
2:今の時代に正しい大麻の選び方とは?
現地で多くの品種を試してきた自分の実感として、従来の「インディカかサティバか」という判断軸は、現在の大麻選びにおいてほとんど意味を持たなくなっています。実際には、同じサティバ表記でも眠気を感じる場合があったり、逆にインディカ表記でも軽い高揚感を覚えることがあり、ラベル通りの体験になるとは限りません。
近年の研究では、体感に影響する中心はTHCやCBDといったカンナビノイドだけではなく、香りや気分の方向性に関わるテルペンの組み合わせであると報告されています。そのため、これからの大麻選びでは、名前や外見よりも成分構成を理解する視点が必要になります。(引用:米国国立医学図書館)
分類ではなく「成分表(カンナビノイドとテルペン)」を見る
サティバやインディカといった分類が不確実である以上、製品を選ぶ際に信頼できるのはパッケージに記載された成分表です。自分がタイの大麻薬局を回ってきた限りでも、体験と成分の相関を見るほうがずっと正確だと感じています。
- THCとCBDなどのカンナビノイド量
- 香りや気分に影響するテルペンの構成
THC量が高いほど多幸感が出やすく、CBDが多いほど落ち着いた体感につながる傾向があります。また、主要なテルペンには以下の特徴があります。
- リモネン(柑橘系)前向きな気分をサポートする傾向
- ミルセン(ハーブ系)休息や鎮静方向の体感を生みやすい
- ピネン(森林系)集中力や思考のクリアさに寄与する可能性
香りの成分であるテルペンが気分の方向性を作り、カンナビノイド比率が体感の強度を決めるという構造を理解しておくと、より自分に合う製品を選びやすくなります。
目的別で選ぶ:集中・睡眠・創造性・ストレスケア
自分が実際に購入するときも、まず「どんな時間を過ごしたいか」から逆算しています。用途ごとに成分の組み合わせを見ると、適したプロファイルを選びやすくなります。
集中したい場面では、CBD・ピネン・リモネンを含む構成が比較的向いていると言われています。睡眠や深い安らぎを求める場合は、鎮静作用が指摘されるミルセンやリナロールを含む製品が選ばれる傾向があります。創造性を高めたいときは、リモネンやカリオフィレンを含むプロファイルが役立つという報告があります。(引用:米国国立医学図書館)
ストレスの緩和を目的とする場合は、CBD量が多いタイプや、THCとCBDのバランスが取れた製品が選ばれやすく、穏やかな気分を保ちやすいとされています。
名前ではなく化学的プロファイルが新しい基準
世界的に知られている「Blue Dream」「OG Kush」「Gelato」といったストレイン名は広く浸透していますが、自分が現地で比べてきた限りでは、同じ名前でも体感が異なることが多くあります。栽培地・育て方・収穫時期によってTHC濃度もテルペン構成も変化し、科学的には「同じ名前=同じ体験」にはなりません。
そのため、海外の信頼度が高い大麻薬局では、ストレイン名ではなく「THC%・CBD%・主要テルペン」を基準におすすめする形が主流になっています。
これからの大麻選びは、名前ではなく自分の目的や体質に合う化学的プロファイルを見ることが大切だと感じています。感覚ではなくデータに基づいて選ぶことが、インディカ/サティバ以降の新しいスタンダードだと言えます。
3:なぜハイブリッドは「サティバからインディカへ」と効き方が変わるのか
自分がタイでハイブリッド品種を吸ってきた経験でも、最初は会話が弾むような軽さがあり、時間が経つと体が沈むようにリラックスへ切り替わることがよくあります。この変化は感覚的なものではなく、成分が体内で作用する順序の違いによって説明できると言われています。
カンナビノイドやテルペンはそれぞれ吸収や代謝のスピードが異なり、その時間差が体感の切り替わりにつながります。この構造を理解すると、ハイブリッド特有の「前半は軽いハイ、後半は深いリラックス」という流れも整理しやすくなります。
① 成分ごとに「効き始める時間」と「ピークのタイミング」が異なる
自分が実際に体感してきた範囲では、サティバ的と言われる明るい気分は比較的早く現れ、リラックス感は少し遅れて訪れるケースが多いです。これは、ハイブリッド品種の中に含まれる成分がそれぞれ異なるスピードで作用するためだと言われています。
たとえば、リモネンなどの柑橘系テルペンは蒸発しやすく、摂取直後に軽さや前向きな気分を引き出す傾向があります。一方で、ミルセンやリナロールのような鎮静系テルペンは時間をかけて血中濃度が高まり、ゆっくりと落ち着いた方向に体感を変えていきます。(引用:米国国立医学図書館)
この時間差によって、前半はサティバ的、後半はインディカ的な体感へ自然に切り替わるという流れが生まれます。
② THCとCBDの代謝スピードが異なり“時間差で気分が切り替わる”
THCは吸入後すぐにCB1受容体と結びつき、気分の高揚や活発さを引き出すと言われています。対してCBDは穏やかに作用し、THCの刺激を緩和する影響があると報告されています。(引用:米国国立医学図書館)
そのため、摂取直後はTHCが主導するアッパーな感覚が現れ、時間が経つにつれてCBDや鎮静系テルペンがゆっくり働き始め、体感が落ち着いた方向へと変化していきます。
「最初はサティバ的で、後からインディカ的に感じる」という体験は、成分の代謝スピードの違いから自然に生まれる流れだと考えられています。
③ テルペンの揮発温度が違うため“吸う順番”が変化する
自分がジョイントを吸ってきた体験からも、吸い始めと終盤で香りが変わることはよくあります。テルペンはそれぞれ沸点が異なり、どの香り成分が先に蒸発するかによって体感も変わると言われています。
吸い始めの温度が低い段階では、リモネンやピネンなど沸点の低い軽い香りが先に揮発し、サティバ的な方向性が出やすくなります。終盤は温度が高くなり、ミルセンやカリオフィレンなど沸点の高い成分が燃焼しやすくなるため、より重めのリラックス感が現れます。(引用:米国国立医学図書館)
吸う温度の変化によってテルペン構成が段階的に変わり、結果として体感もシフトするという仕組みです。
4:インディカもサティバも「今は混ざり合った一つの植物」
自分がタイでさまざまなストレインを見てきた経験でも、インディカとサティバを外見だけで区別することはほとんどできません。最近の研究では、長年続いてきた交配によって市場に出回る大麻の多くが遺伝的にハイブリッド化しているという報告があります。(引用:米国国立医学図書館)
このため、DNAレベルで明確に「インディカ」「サティバ」と区分することは難しく、現在流通している大麻は両方の特徴が自然に混ざり合った一つの植物だと理解されています。自分が実際に吸ってきた感覚でも、体感が時間によって変化することが多く、分類の枠だけでは説明しきれない印象があります。
体感をつくる中心は、品種名ではなくTHCやCBDの比率、さらにリモネン・ピネン・ミルセンなどのテルペン構成だと言われています。明るい香り成分が多いストレインでは前向きな気分が出やすく、重めの香り成分が多い場合はリラックス方向に働く傾向があります。
そのため、今の大麻選びでは「インディカかサティバか」ではなく、自分がどのような気分や時間を求めているかを基準にする方が合理的だと考えています。名前よりも成分や香り、使用シーンの相性を理解して選ぶことが、現代的で安全な向き合い方につながります。
※この記事は2025/11/12に公開した情報になります。
※当サイトに掲載された情報については、その内容の正確性等に対して、一切保障するものではありません。
※当サイトに掲載された情報については、投稿者の個人的な私感が含まれている場合があります。
※ご利用等、閲覧者自身のご判断で行なうようお願い致します。
※当ウェブサイトに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切責任を負いかねます。
THAILAND CANNABIS GUIDE
タイで医療大麻を吸うなら、次に読むべき4つ
この記事を読み終えたあとに「ホテル」「安全」「お店」「最新情報(LINE)」の順で行動できるように、重要な情報だけをまとめています。




個人的にオススメの大麻薬局

Green House Thong Lo
トンロー

Tropical Thunder Dispensary
ジョムティエン
バンコクにあるオススメの大麻薬局

Siam Green Cannabis Co Phrom Phong
プロンポン

High Craft
アソーク

Amélie
チャイナタウン

Cannabis X
トンロー
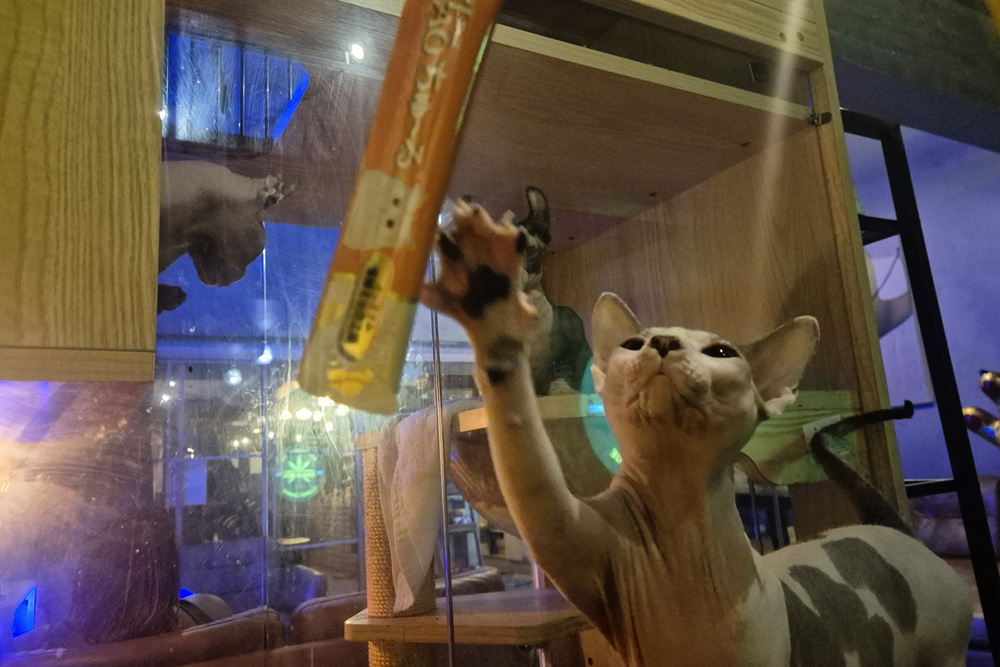
Ganja Man
アソーク

Revana Café (Silom)
シーロム

Fat Buds
オンヌット

BABY BLUNT
エカマイ
パタヤにあるオススメの大麻薬局

Tropical Thunder Dispensary
ジョムティエン

The Budtender
ウォーキングストリート

Nirvana Raggaebar
ウォーキングストリート

WICHAI PAIPAR SHOP
セントラルパタヤロード

Highsiam Cannabis Dispensary
サードロード

Nuggs Premium Cannabis
サードロード